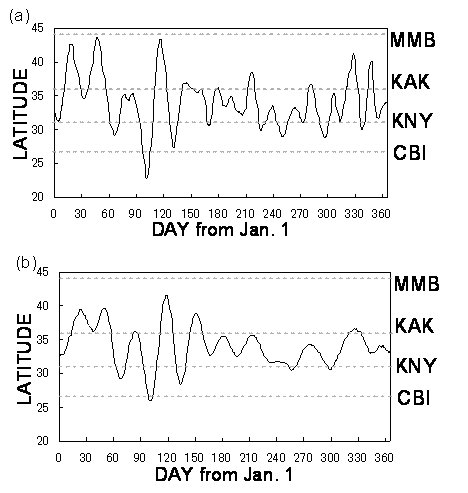地上での観測される地磁気には、太陽から放出されるプラズマ粒子や光が、地球磁場の領域(磁気圏)や、大気上層の気体が電離してイオンと電子が存在する層(電離圏)に作用して発生する磁場変動が見られる。この磁場変動には、主として、地球の昼間側で電離圏に流れる電流が作る変動成分(Sq:磁気的に静穏な日変動成分)や、磁気圏に流れる電流が作る変動成分(D:ときに磁気嵐と呼ばれる地磁気の顕著な減少を伴う磁気的な擾乱成分)がある。これらは同時に観測されるので、両者を分離するのがむずかしいことはよく知られている。これまでは地磁気観測に基づく研究として、静穏日を対象にした電離圏電流系の調査や、静穏日を基準とした磁気嵐などの地磁気変動の調査が行われてきた。一方で、世界時(UT)で国際的に月毎に5日の静穏日が指定されて、この国際静穏日と重なる時間の多い日を現地時 (LT)の静穏日とするので、現地での5静穏日は必ずしも静穏とは限らないことが指摘されている。しかし、SqとDの分離の問題や、現地の5静穏日の静穏日としての代表性について議論した調査研究はまだ少ない。本研究では、時間軸上での局所的変化の検出が可能なwavelet多重解像(データ分解を複数回行う画像処理的手法)により、従来の統計的分析手法では困難であった地磁気データのSqとDへの分離を試みた。
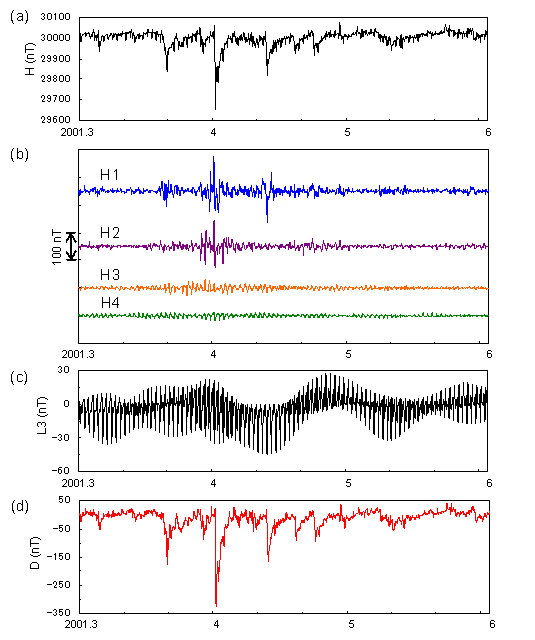
図1に、柿岡の地磁気観測の毎時値に対してwavelet多重解像を用いた結果を示す。図1aは2001年3〜5月までの地磁気水平成分(H)の観測値である。とりわけ4月上旬に磁気嵐のため地磁気に顕著な減少が見られる。3、4月に比較して5月は磁気嵐のような地磁気擾乱の影響が少なかったことが分かる。図1bは、4回のwavelet多重解像により分解した高周波成分である。分解した回数の順にH1からH4まで載せており、H1側ほど高周波である。H1は、主に地磁気擾乱による急変部やノイズを検出し、H2とH3は、H1で検出されなかった急変部の成分を検出している。H4は、このような急変部の局所的な成分よりむしろ、もっと長周期の変動成分を検出しているように見える。従って、この場合、3回のwavelet多重解像により分解したH1〜H3が地磁気擾乱の成分を含むと考えられるので、残りの低周波成分(L3)をSqとみなす(図1c)。観測値からL3と永年変化を除いてDを分離することができる(図1d)。
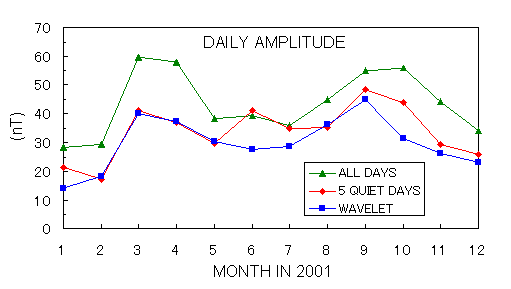
図2は、2001年の地磁気水平成分について、夜間値を結ぶ線形補間と観測値との差について、日最大と日最小の差の単純月平均(緑線)、5静穏日の月平均(赤線)を示し、また、3回のwavelet多重解像によるL3の日最大と日最小の差の単純月平均(青線)を示す。いずれも春と秋は変動幅が大きい季節変化を示す。緑線と青線との差は、主にDの分離による効果である。5静穏日とwavelet多重解像は、比較的差の大きな1、6、7、10月を除き、図1に示した3〜5月を含んだ多くの月で良い対応を示す。この結果は、これら対応の良い月については、5静穏日は静穏日としての代表性をもつことを示唆すると言える。
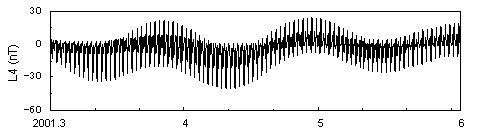
図1cは、Dの影響を分離した後の日変動であるので、これに基づきSqの解析が可能である。図3は、4回目のwavelet多重解像を施した低周波成分(L4)であり、図1cに示したL3と比べておよそ30日の周期(太陽の自転27日周期に近い)をよりはっきりと示す。L3よりL4の方が形態的特徴がシンプルに現れることから、Sqの特徴について調べる上ではL4を用いる方に利点がある場合がある。図4は、柿岡、女満別、鹿屋、父島の4地点から推定した北半球のSq電流系の中心緯度である。図4aはL3を、図4bはL4をそれぞれ使用して推定した結果である。両者はともに、Sq電流系の中心が春季に女満別と父島付近まで移動していることを示す。図4aは、図4bに比べて高周波成分を含むことが分かる。推定したSq電流系の中心緯度の変動周期について、あらためて主成分を分析するまでもなく、図4bは、図4aに含まれる主な成分(およそ30日の周期)を示している。
地磁気日変動について、本解析では、地磁気擾乱の除去に伴い、図1cに示した変動周期より早い周期の変動成分は分離されてはいるが、擾乱の影響を除去したことにより信頼できる日変動を評価していると言える(図2)。その活用として、Sq電流系の中心緯度の推定において、wavelet多重解像の利点が示された(図4)