研究代表者:笹岡 雅宏
地磁気観測所では地殻変動や地震活動等の地殻活動と地磁気の変化との関連を調査する目的で、東京大学地震研究所(以下、地震研)と連携し伊豆半島東部で地磁気全磁力観測を行っている(図1)。伊豆半島東部の群発地震活動は、主にマグマ貫入に伴って発生すると考えられている。マグマ貫入に伴う火山性の群発地震の場合は、岩石の持つ磁気の強さが岩石の温度や応力に応じて増減するため地磁気が変化する。2011年は当所観測地点を含む領域において7月中旬と9月下旬に数日にわたる群発地震が発生した。図2は、当所及び地震研の観測点について、柿岡基準の単純全磁力差(黒線)、地磁気擾乱を補正した結果(赤線)、年周変化(緑線)、並びにそれぞれのトレンド(黒直線)を示す。図3は、図2中の年周変化とトレンドを差し引いた各観測点の全磁力変動のプロットを示す。各観測点では欠測が多く見られるため必ずしも明瞭ではない期間もあるが、概ね以下の特徴が見つかった。①2011年6月下旬〜10月中旬にかけてIK2以外では全磁力の増加(プラスの偏差)が見られる。②2011年10月中旬〜11月中旬にかけてITB、YOB及びKWNでは全磁力の減少(マイナスの偏差)が見られる。
2011年9月下旬の群発地震の終息後に、上記②の全磁力の減少が見られたが、それ以降全磁力変動に顕著な偏差は全体に見られなくなった。2011年の全磁力の増減は、東北地方太平洋沖地震後に各地で地震活動が活発化した時期にあたり、火山性よりは断層のずれが主な要因に挙げられるが、KWNは2011年11月中旬以降にも全磁力の減少が見られITBやYOBと同期していない点などがあり、観測された全磁力変化は主に地下の熱水活動に起因するものではないかと推測する。地震発生頻度の高い領域に近い観測点では上記①のように全磁力の増加が見られ、特に震央に近い観測点では上記②のように全磁力の減少が特徴的に見られた。このような特長的な全磁力の変化が2012年には見られなくなり年周変化が目立ち始めたことと、2011年と比べ2012年の地震活動が静穏化していることとは調和的である。
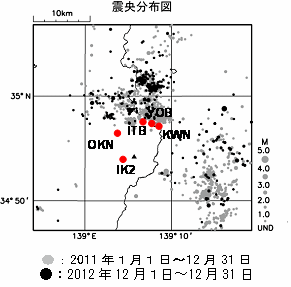
図1 2011年と2012年の震央分布図、並びに玖須美元和田観測点(ITB)及び地震研観測点(YOB、KWN、OKN、IK2)の配置。群発地震が2回(7月中旬と9月下旬)発生した2011年に比べ、2012年の地震活動は静穏に推移した。
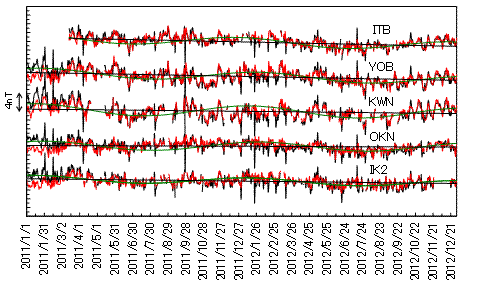
図2 玖須美元和田観測点(ITB)と地震研観測点(YOB、KWN、OKN、IK2)の解析結果比較(2011.01.01−2012.12.31)。 柿岡基準の単純全磁力差(黒線)、Dst指数及び夜間偏差の月別標準偏差(σ)に基づいて推定された静穏レベルを用いた擾乱補正の結果(赤線)、年周変化(緑線)。それぞれにトレンド(黒直線)を付加。
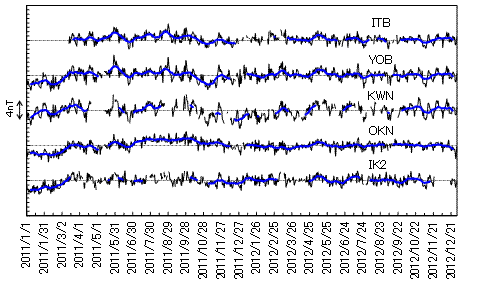
図3 玖須美元和田観測点(ITB)と地震研観測点(YOB、KWN、OKN、IK2)の地磁気全磁力の変動比較(2011.01.01−2012.12.31)。 各観測点について、図4中の擾乱補正後の解析結果から年周変化とトレンドを差し引いてプロット。青線は潮汐周期を無視するための15日間移動平均を示す。
